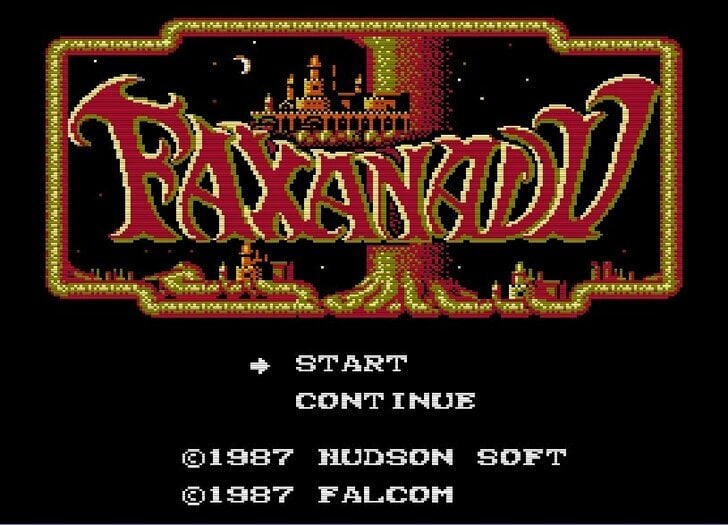
グラフィックが美しく、BGMも素晴らしいアーケードゲームやパソコンゲームに憧れていたファミコン世代は多いはず。そんな人気タイトルがファミコンに移植されることもありましたが、ゲームハードの性能差もあって完全移植は現実的に不可能でした。
それは仕方ないことだと分かってはいましたが、オリジナルを自宅で思う存分に遊んでみたいと思ったものです。
時には、そのままファミコンに移植するのを諦めたのか、完全に別のゲームになってしまったものもありました。「なんじゃこりゃ……」と思いながら遊んでみたら、実は移植元のオリジナルとは違う面白さがあったゲームもあったのです。
今回はそんな変わり種の移植ソフトを振り返っていきます。
※本記事には各作品の内容を含みます。
■まるで別モノ? ゲームジャンルまで変更になった怪作
移植元とまったく違う内容になってしまったファミコンソフトといえば、『源平討魔伝』(ナムコ)を真っ先に思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。
アーケード版の『源平討魔伝』はナムコが誇る屈指の名作。3つのモード(横スクロールアクションの小モード、トップビュー視点の平面モード、巨大キャラが横スクロールで戦うBIGモード)で構成されたアクションゲームで、当時アーケードゲームでも珍しかった巨大なキャラクターが叫びながら剣を振り回す姿が印象的でした。
それがファミコンに移植されると、なんと日本地図やメタルフィギュアなどが付属になった、最大4人プレイが可能な「コンピュータボードゲーム」となっていたのです。
とはいえ実はボードゲーム要素はほとんどなく、1人プレイ時は見下ろし型のフィールドを冒険し、コマンドバトル式で敵と戦うRPG仕立てです。それも『ドラクエ』のようにストーリーを追うのではなく、ランダムに配置された「三種の神器」を集めつつ、主人公の景清を強化してボスを倒すという内容でした。
魔物を倒して徳(経験値)を集め、それを神社で消費してプレイヤーが自分で各種パラメータに割り振って景清を強くしていきます。
そして「三種の神器」とは、アーケード版でラスボスの源頼朝を倒すのに必要だった「草薙剣」「八咫鏡」「八尺瓊勾玉」のこと。ファミコン版でも、これをすべて集める必要があります。
実は、ファミコン版で三種の神器がどの国で手に入るのかは完全にランダム。行きづらい国に配置されようものならリセットしてやり直したほうが手っ取り早いのです。
かなり運の要素が強いのですが、今思えばローグライクのゲームをプレイしているようなちょっとしたワクワク感がありました。
景清が弱い序盤さえ切り抜けられたら、徳(経験値)を稼ぐ効率が大幅にアップ。どんどん景清を強化していけば、城主やラスボスの頼朝すらラクに倒せるようになります。
RPG風にゲーム性が変わりながらも、世界観や登場キャラはしっかり『源平討魔伝』を踏襲。しかもファミコン版のBGMもアーケード版と同様に中潟憲雄氏が手がけており、原曲を知っている人なら義経、弁慶、頼朝とのバトル時はテンションが上がるはずです。
慣れないうちは攻略の糸口がつかみづらく戸惑いますが、遊び方が分かってくれば思った以上に楽しめるファミコン版『源平討魔伝』。当時、食わず嫌いでプレイしなかった人にこそ、ぜひ試していただきたい一作です。


