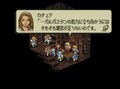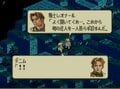■画期的な戦闘システム
同作では「ウエイトターンシステム」という独自の戦闘システムが導入されている。ターン制ではなく、わかりやすく言えば、「敵、味方に関係なく、身軽なユニットの順に行動ができる」という点だ。素早いユニットは行動開始が早い。しかも次の行動開始までも早くなるので、場合によっては、あるユニットが2回行動する間に3回行動できたりするユニットも存在する。そのあたりが戦略を複雑にしている。
他にも「高低差」や「ユニットの向き」というこれまでにない概念が導入されている。たとえば、低いところから高いところにいる敵に弓を放っても届かなかったり、逆に高いところから低いところに弓を放つと、射程以上の遠くまで届くといったこともある。
また、正面から敵を攻撃するより背後から攻撃する方が命中率が高いといった要素も独特である。
こういったリアルな要素をふんだんに盛り込んでいるが、そのせいか、力が強いが動きは遅いといういわゆる脳筋型のユニットの影が薄く、アーチャーなどの弓兵や動きの素早いニンジャなど、他のゲームでは影の薄いキャラが大活躍するというのも同作の特徴的な点だろう。
■本編より長い?死者の宮殿
このゲームを語るうえで欠かせないのが、「死者の宮殿」と呼ばれるダンジョンである。このダンジョンはクリアしなくてもストーリーには影響のないおまけのようなダンジョンなのだが、そのボリューム感たるやハンパない。
なんといっても地下100階まであるという長すぎるダンジョン。出てくる敵もこれまでに出会ったことのないような敵ばかりで気が抜けない。途中でやられてしまうとリセットということも多々あるため、死者の宮殿をクリアするだけで本編を最初から最後までクリアするのと同じぐらいの時間がかかってしまうのではないかというぐらいのボリュームである。
これはもはやおまけダンジョンと言ってはいけない。もう立派に別ゲームとして成り立っているぐらいだ。
相当長くて難解なダンジョンなのだが、貴重で強力なアイテムや魔法を多数入手できるため、本編そっちのけでのめり込んでしまい、メインのストーリーを忘れてしまうというのは、もはやお約束かもしれない。
以上、簡単ではあるが『タクティクスオウガ』のすごかったポイントをまとめた。スーパーファミコンのスペックで表現できるほぼ最高の内容が提供されており、長年にわたり愛されている名作ということがわかる。
リメイクだけでなく、のちにプレイステーションでも発売された『ファイナルファンタジータクティクス』(スクウェア/1997年)にもそのスタンスが受け継がれており、この『タクティクスオウガ』がゲーム界にもたらしたものは大きかったといえるだろう。