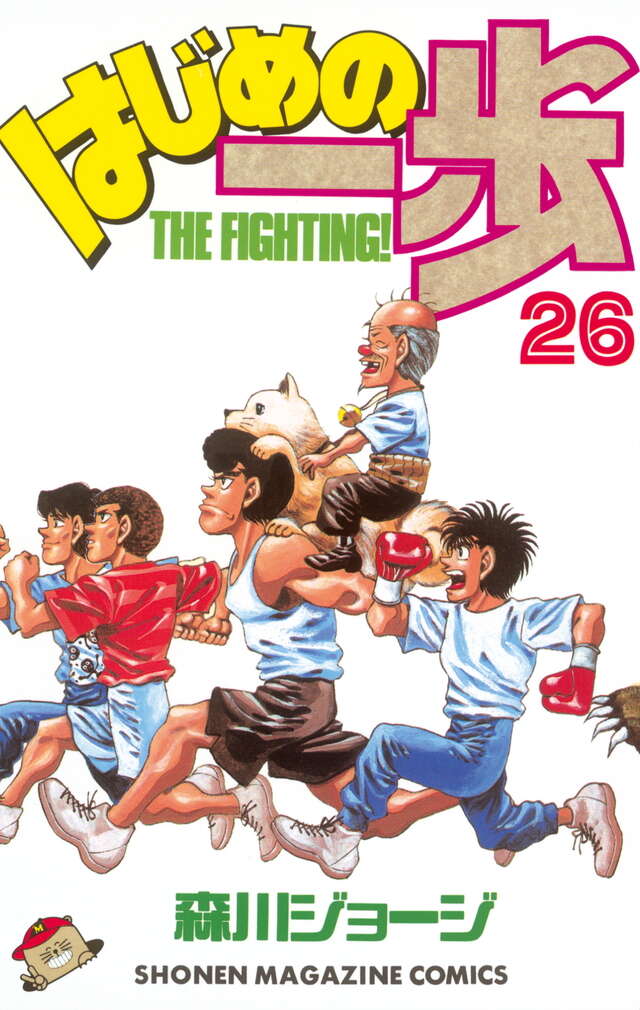
1989年から連載が始まった、森川ジョージ氏の長編ボクシング漫画『はじめの一歩』。
本作では現在、若い世代が躍動している。ウォーリー、間柴了らが次々と世界の頂点に挑み、『週刊少年マガジン』(講談社)では、千堂武士の世界戦が連載されている。ボクシングというスポーツの性質上、肉体的に充実した若い才能にスポットライトが当たるのは当然といえるだろう。
だが、若さだけが全てじゃないのが『はじめの一歩』の魅力である。本作では、ボクサーとして全盛期を過ぎたベテランが活躍する試合も数多く描かれており、中には世界の強豪を苦しめた男もいる。ベテランならではの知恵と経験は、ときに何よりも鋭い武器になるのだ。
そこで今回は、『はじめの一歩』で見事な奮闘を見せた「いぶし銀」のベテランボクサーたちを紹介しよう。
※本記事には作品の内容を含みます
■天性のセンスは現代でも通用した? 猫田銀八
まずは、コミックス第45巻から始まる「戦後編」で活躍した猫田銀八を見てみよう。現代では山奥に住む陽気な老人として描かれている猫田だが、かつては鴨川源二と共に拳闘の世界で名を馳せた一流のボクサーだった。
終戦後を舞台にした「戦後編」時点で、すでに全盛期を過ぎていた猫田だが、その活躍は鮮烈で印象深いものであった。パンチドランカー症状に悩まされながらも、猫田は愛する女性・ユキのために米兵ボクサー、ラルフ・アンダーソンとの試合に臨む。
圧倒的な体格と科学的なボクシング技術を併せ持つアンダーソンは紛れもない強敵だったが、猫田は山奥育ちで培った野生の勘を武器に、この巨人を見事に翻弄する。当たれば無事では済まないアンダーソンのパンチを紙一重でかわし、カミソリのようにキレ味鋭いパンチを叩きこむ戦いぶりは、親友の鴨川をして「芸術だ!」と言わしめるほどであった。
だが、後頭部を打つ反則技「ラビットパンチ」を受けた猫田はパンチドランカーの症状をぶり返してしまい、あえなく敗北してしまう。このアンダーソンの反則さえなければ、猫田の勝利の可能性は高かったはずだ。
ボクサーとして盛りを過ぎた時期に、体格で勝るアメリカ人ボクサーと互角以上に渡り合った猫田のセンスは素晴らしい。その類まれなボクシングセンスは、現代ボクシングのリングでも十分に通用したのではないだろうか。
■試合によって作戦を変える知能派ボクサー! 木村達也
次は、鴨川ジムを代表するいぶし銀のベテラン、木村達也だ。木村といえば、間柴了との日本ジュニアライト級タイトルマッチで見せた「ドラゴン・フィッシュブロー」が特に有名だ。ボディを打ち続けて相手の気を逸らし、相手の意識の外から右を打ちこむこのコンビネーションは、間柴を限界まで追い詰めた木村の代名詞といっていいだろう。
しかし、木村の真骨頂はこの必殺技そのものではなく、それを思いついた知性にあるというべきだろう。そもそも彼がドラゴン・フィッシュブローにたどり着いた経緯は、間柴を攻略するための方法を考えるところから始まっている。
すべてにおいて格上の間柴を倒すには、弱点の顎を打ち抜き、意識を刈り取るしかない。だが、身長180cm近い間柴はリーチが長く、顎の位置も高いため、普通のパンチでは届かない。この八方塞がりに思える難題に対し、それでも木村は考え続けた。そして、ペットのアロワナが大ジャンプして餌を食べる様子から着想を得て、ついにドラゴン・フィッシュブローを閃くのだ。
対戦相手の弱点を分析し、効果的な作戦を実行するクレバーさこそが木村の持ち味であり、ベテランならではの強みといえる。もっとも、その冷静さがときに慎重すぎる展開を招き、勝利を逃した試合も少なくないという。そんな少し抜けている部分も、鴨川ジムの名物コンビ「青木村」の一角としての彼らしい魅力なのかもしれない。


