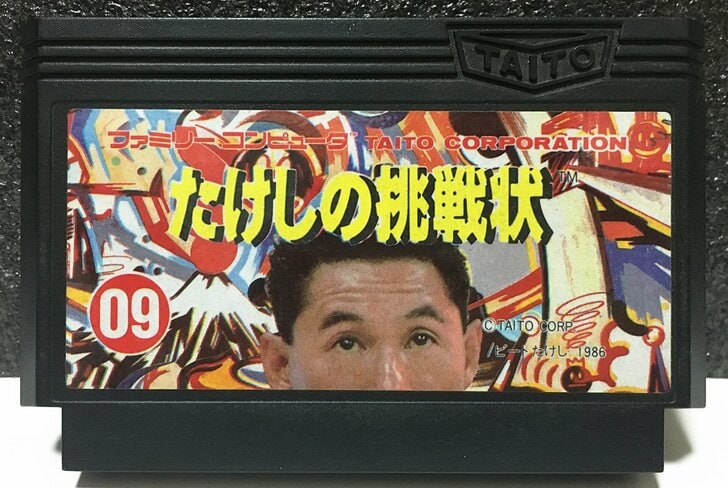
1983年に任天堂から『ファミリーコンピュータ』(以下、ファミコン)が発売され、社会現象を巻き起こすほどの数々の人気ゲームが次々と誕生した。
現在に至るまでシリーズが続く不朽の名作や、その尖った作風で強烈なインパクトを残した作品など、いずれも唯一無二の個性的なゲーム性でプレイヤーを魅了してきた。
しかし、そんな名作ファミコンソフトの中には、普段プレイをしているだけではなかなか分からない、奥深い世界設定が説明書に記されているケースも少なくない。
そこで、思わず見過ごしてしまいがちな、名作ファミコンタイトルの「意外な公式設定」について振り返っていこう。
■さらわれたピーチ姫の意外な能力とは?『スーパーマリオブラザーズ』
1985年に発売された横スクロールアクションゲーム『スーパーマリオブラザーズ』は、今や任天堂の看板ともいえる国民的人気シリーズである。シンプルなアクションでありながら、思わずのめり込んでしまうステージギミック、軽快なテンポとクリア時の達成感が多くのプレイヤーを虜にした。
空中に浮くブロックを壊したり、パワーアップアイテムがキノコだったり、迫ってくる敵が亀だったりと、独自の世界観もその魅力の一つだろう。
実はこの『マリオ』の世界観にまつわる重要な設定が、説明書に記載されていることをご存じだろうか。
説明書に収録された「ものがたり」によると、なんと本作のボスキャラである大魔王クッパは、王国にいたキノコ一族を強力な魔法によって岩やレンガに変えてしまったという。
しかも、この魔法を解くことができるのは、クッパにさらわれているピーチ姫ただ一人。つまりマリオは、クッパに囚われたピーチ姫を救い出し、滅びてしまった王国を元の姿に戻すという重大な使命を背負っていたのだ。
ちなみに、最初のステージから登場する敵キャラ・クリボーにも、意外な誕生秘話がある。制作者がのちに語ったインタビューによると、このクリボー、当初は「キノコ王国の裏切り者」というシリアスな設定があり、見た目も「黒いマッシュルーム」をイメージしていたという。だが、いざ完成したビジュアルが「栗」に見えたことから、現在の「クリボー」という名前に落ち着いたのだとか。
今やおなじみとなった『マリオ』シリーズのキャラクターたちだが、その裏に隠された意外な公式設定に驚かされてしまう。
■道具や呪文の説明にも思わず心が躍る…『ドラゴンクエスト』
1986年にエニックス(現:スクウェア・エニックス)より発売された『ドラゴンクエスト』は、日本にRPGブームを巻き起こした先駆けであり、まさに伝説的な作品である。練り込まれたファンタジーの世界観や壮大な物語は、圧倒的な没入感でプレイヤーを夢中にさせた。
そんな本作もまた、付属の説明書に世界観を紐解くさまざまな情報が記されていた。
特に興味深いのが、作中に登場する武器や道具などのアイテムや呪文に関する説明である。
たとえば、オーソドックスな回復アイテムである「やくそう」は、マンドラゴラの根とヨモギの葉をすりつぶして作られるという、詳しい製法までが記載されている。
また、一瞬で街に戻れる「キメラのつばさ」は、モンスターのキメラが落雷で死んだ後に残った本物の翼である……といった、実に神秘的な設定が明かされているのだ。
こうした細やかな設定は、続編である『ドラゴンクエストII 悪霊の神々』にもある。
『ドラクエ2』で特に衝撃的なのが、呪文の背景設定だ。たとえば、対象を即死させる「ザラキ」は、相手の体内の血を一瞬で凝固させ死に至らしめるという、実に恐ろしい設定がある。
また、少し意外だったのが、全体に大ダメージを与える「イオナズン」だ。実はこれ、もともと神々が地上の人々に啓示を与えるための手段であったが、神の力が強大すぎたのか、空中のすべてのエネルギーを集め、相手の頭上で大爆発を引き起こす呪文へと変わってしまったという由来がある。
どれもこれも作中では語られないまさかの設定ばかり。ちょっとした道具や呪文に隠された背景を知ると、思わず想像力を刺激されてしまうことだろう。


