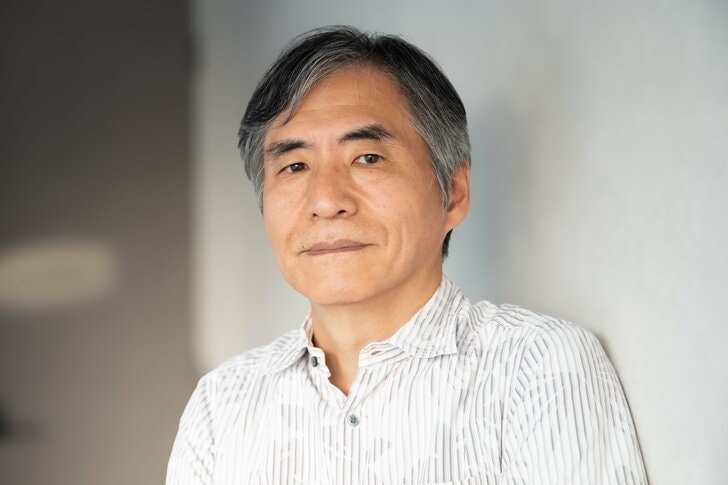
旗揚げから45周年を迎える劇団☆新感線が、2025年9月より劇団☆新感線45周年興行・秋冬公演 チャンピオンまつり いのうえ歌舞伎『爆烈忠臣蔵~桜吹雪THUNDERSTRUCK』を上演する。本公演の脚本を担当する座付き作家の中島かずき氏は、1985年から40年間新感線とともに走り続けてきた。
2002年には『アテルイ』で第2回朝日舞台芸術賞・秋元松代賞、第47回岸田國士戯曲賞を受賞。2017~2018年には『髑髏城の七人』のロングラン公演を実施。5シーズンに分けて、シーズンごとに異なるキャストと脚本・演出で上演するという試みにも挑んだ。さらに舞台以外でも、アニメや特撮ヒーロー、ドラマ作品も手掛け、活動の幅を広げている。
そんな中島氏にとって、ターニングポイントになった作品、そして彼の脚本家としてのキャリアを広げた作品とはなんだろうか。話を聞いた。
――中島さんは劇団☆新感線で、改作再演も含めて62本もの作品を書き下ろされています。その中で、中島さんのキャリアにとってターニングポイントになった作品を挙げるとすると、どの作品になりますか?
中島かずき(以下、中島):やっぱり『阿修羅城の瞳』(1987年初演)ですね。自分が「書ける」という自信を持たせてくれたのは、この作品なんです。あのころは28歳でしたが、この作品を書いたことで、「自分はもっと書けるかもしれない」という可能性みたいなものを感じました。自分の扉をひとつ開くことができたのは、間違いなく『阿修羅城の瞳』でしたね。
――『阿修羅城の瞳』は2000年、2003年に再演され、今年には宝塚星組がミュージカル化するなど劇団☆新感線の代表的な演目になりました。そもそも『阿修羅城の瞳』はどんなきっかけで執筆することになったのでしょうか。
中島 いのうえ(ひでのり)くん(劇団☆新感線主宰・演出)と何をやろうかと打ち合わせしたときに、彼から「恋をすると、鬼になる女性の話をやってくれ」と言われたんです。じゃあ、鬼って何だろうと考えていって。魔物退治の話が好きだったので、鬼殺しと鬼の話にしようと思ったんですが、今と違って、日本の呪術や陰陽師関係の資料などはあまりなくて。
当時はまだ夢枕獏さんが『陰陽師』を発表される前だったので、安倍晴明の存在は本当にマイナーだったんです。おそらくエンタメとして世の中に出ていたのは、荒俣宏さんの『帝都物語』くらいだったんじゃないかな。
だから、資料も荒俣さんの本以外にはほとんどなくて。でも、いろいろと探してみると、当たっていく資料がとにかく面白い。物語の渦のようなものに踏み込んでいくような感じがあって、ひとつひとつ新しいことを知るたびに、蒙を啓かれていくような感覚がありましたね。
――物語の渦に踏み込んでいく。中島さんは過去のインタビューで、その物語が生まれてくる過程を「玉(物語の玉)」になぞらえていたことがありましたね。
中島:そうなんですよ。『阿修羅城の瞳』を書いているときに、物語って玉のようなものだなっていうイメージがあったんです。人間たちがいる世界とは違う、別の空間に集合無意識の塊みたいなものがあって、そこには人がこれまでに培ってきた物語という糸がグルグルに絡み合って玉のようになっている。我々創作者は、その物語玉の端から出ている糸のようなものを引っ張っていく。
その創作者の糸の引っ張り方が上手だとスルスルと糸が抜けてきて、その糸がどんな色なのか、どんな長さなのかわかるし、想像もしていないような色をしていることもある。でも、下手な引っ張り方をすると、ブツブツ切れてしまう。
そのブツブツ切れたものをつなぎあわせていくと、ノッキングするような物語になってしまう。僕たち創作者に必要なのは、玉から糸をすんなりと引き抜くテクニックじゃないのか?……みたいなことを感じていた時期があるんです。
――集合無意識から、物語を引き出すような感覚。
中島:物語玉ではないですが、似たようなことを、同じ時期に島本和彦さんが漫画で書いていたり、ほかにも作家の皆川博子さんとか同じようなことを言っている人がいたんですよね。みんなどうしてそう感じたのかはわからないけれど、僕だけじゃなかった。おそらく創作者の無意識の中に、共通の感覚があるんだと思うんです。
――『阿修羅城の瞳』を執筆したころは、中島さんは会社にお勤めでしたよね?
中島:そのころはもう『週刊漫画アクション』編集部にいました。国友やすゆき先生の『JUNK BOY(ジャンク・ボーイ)』という作品を担当していたころです。


